ついにこの古典中の古典を読む。いまさらな古典でガッカリするのかと思いきや、さすが現在までにいたる吸血鬼というモンスターを決定づけた作品、地力というか、作品そのものに宿るパワーがとんでもないです。少々長いかもしれませんが、未読なら今さらかよと思わず、その原点にして決定版といえるこの名作を手に取ってみてはどうでしょうか。とにかくまず、面白すぎるから。
まずこの作品はその記述様式が特異であり、全編が様々な媒体による記述の集積によって成り立っているのです。登場人物それぞれの日記やメモ、手紙といった手記や、新聞記事、はては蝋管による記録など、当時のあらゆる記録媒体によって吸血鬼についての記述が積み重なり、物語を形成しているのです。元々、吸血鬼というものが東欧の民間伝承から発したものであり、著者のブラム・ストーカーが長年、その伝承の記録を渉猟したということですが、まるでその過程を物語としたような、そんな誰かのしたためた記録ですべてが成り立っている作品なのです。
誰かの記述であるということ、それが怪談としてのこの物語を秀逸なものにしています。吸血鬼という存在がよく分からないでいる人々が、怪奇にさいなまれていく様子、そのよく分からない不安感が恐怖感へと昇華していくさまが記録形式により読者へリアリティを持って迫ってきます。特にデメテル号のくだりは出色の怪奇話となっているのではないでしょうか。犬、泥の詰まった棺桶といった道具立ても見事。
そしてなんといってもルーシーの首元についた、ささくれ立った跡の不思議とその後の衰弱の様子。よく分からないがしかし、死の臭いのする何者かがゆっくりと迫ってくるのは今読んでも怖い。後半、吸血鬼の存在が明らかになり、ヘルシング教授率いる討伐隊がドラキュラを撃退し、トランシルバニアまで追いかけていく冒険小説的な体裁になりますが、そこもまた面白く読めます。多視点で追い込んでゆく過程は記録形式が生きてきます。
この作品のドラキュラ伯爵は後続作品に出てくるような暴力的な力で人を襲ったりする怪物的な存在というよりは、どこか疫病的と言いますか幽霊的な趣が強いです。どこからともなく部屋に入りこみ、少しづつ対象を死に近づけてゆく存在。実態がどこかあやふやだからこそ怖い。吸血鬼の恐怖の本質というのは、得体の知れないものにふらりとテリトリーに侵入される恐怖なのではないか。土俗性を帯びていた東欧の伝承が近代化された都市の一室に忍び込む。そういえばこの領域に侵入される恐怖として、ミステリ者としては50年以上も遡る1841年にポーが書いた「モルグ街の恐怖」が思い出されました。恐怖の対象が遠くの異国からやってくるというのも共通しています。この作品もある意味、探偵役的なヘルシング教授が現れてからの後半は吸血鬼の足取りをたどる捜査小説的な趣をおびていて、吸血鬼の行動やその移動ルートを推理してゆく場面はかなり推理小説しています。
そもそも出来事を詳細に記述してゆくというのも探偵小説と重なり合う部分があり、怪物についての記録の物語――犯人についての記録の物語という感じで探偵小説と親和性があるようにも感じました。この小説自体が吸血鬼についての証言、出来事を詳細に収集してゆく――それは自身の記録を詳細に収集していた江戸川乱歩の姿が思い浮かび、シャーロックホームズが1891年で先立つこと6年ほど前ということで、やはり、探偵小説との関連性、縁のようなものを感じさせます。ディテールを収集し、それを参照することで推論に至るというのは、推理小説の領域に他ならない。
しかし、この小説は最後の最後でそこに大きな亀裂を入れる。
私は長いこと金庫にしまっておいた当時の文章を、そのとき久しぶりで取り出して見た。読み返してみて驚いたことは、記録が構成されているこれだけの山のような材料の中に、これこそがただ一つの真正な記録だというものがないことであった。
膨大な記録のテキストの山、それによって成り立っていたはずのこの作品を根底から覆すような爆弾が、きわめてさりげなく置かれる。ただ一つの真正な記録がないのなら、ではそれによって指摘されている“犯人”ドラキュラは、「真正」なものだったのか。伯爵が最後に塵と化し、文字通り消えさったようにして、「犯人」もまた消失してしまう。これは何だ。ほとんどアンチミステリといっていい様相ではないか。
とはいえ、自己否定、自己言及もまたミステリの得意技だ。この作品は早すぎただけとも言える。むしろこの作品のミステリ的先駆性はそこにあるのではないか。シャーロック・ホームズが現れ、そのライヴァルたちが陸続として活躍し始める世紀末。科学が称揚され、その科学的姿勢は詳細な証言、証拠といったものをテキスト化し、データ化する。それによってヒーローたちは世紀末の闇を照らす。しかし、やがて、そのテキストそのものを脅かすトリックの存在がアガサ・クリスティによって決定的な形で暴露される。
書かれたテキストは果たして真実なのか? クリスティの問題作はそのテキスト――書き手において本作を逆転させたような存在でもあり、本作がどの程度影響を与えたのか気になるところだ。
ともかく、探偵小説が本格的に誕生し、ジャンルを形成し始めたその周辺部ではすでに亀裂が走っていたと考えると、なかなか面白い。推理の根拠が消失することで、テキストの集積によってその円環の中心の空として存在していた伯爵も消え去る。ここに至り、推理小説的な領域から怪奇小説的な領域へとその書かれた存在は越境してゆく。
土地を、部屋を越境してきたドラキュラは、推理小説的に悪魔祓いされる形で追い返されるが、ついにはその推理小説的な範疇からも越境してしまうのだ。確かにテキストの否定はそれでもミステリ的な領域ではある。しかし、『吸血鬼ドラキュラ』はその書かれた「存在」が消失することで、ミステリ的な領域からもするりと抜け去ってしまったのだ。
おわりに
『吸血鬼ドラキュラ』と推理小説との関連性は、以下の本が示唆に富み、ものすごく面白いので、是非読んで欲しい。この拙文の参考とした「勝利のテクスト」以外にも面白い論考が満載です。ほんと俺の文章なんかどうでもいいから読め。読むんだ。

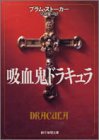


![アトミック・ブロンド スペシャル・プライス [Blu-ray] アトミック・ブロンド スペシャル・プライス [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PPUdxD3ZL._SL160_.jpg)